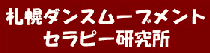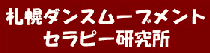〇 国内では一般的に「ダンスセラピー」と呼ばれていますが、
正式名称は「ダンス・ムーブメント・セラピー」です。日本ダンス・セラピー協会は、アメリカ・ダンス・ムーブメント協会(ADTA: American Dance Movement Association)による影響もあり、「ダンスに限定されず、様々な身体的な動き・動作である<ムーブメント>を心理療法的に用いる」ことを想定しています。
〇ダンスセラピー実践技法:「ボディラーニング」とは―。
上に示したように「ダンスセラピー」は、正確には「a)ダンス」「b)ムーブメント」「c)セラピー」という三つの要素から構成されています。
ダンスの経験値の高い方は⇒「ムーブメント」と「セラピー」の新たな理解が重要となるでしょうし、心理関係の経験値の高い方は⇒「ダンス」と「ムーブメント」の経験と新たな理解が重要になってきます―。
- ボディラーニングとは
ダンスの様式や音楽によって覆われてしまいがちな、本人の <こころとからだの生のあり方> を、あらためて見いだすアプローチです。
- 「音楽に合わせるダンスとは異なり、カウントなどに関わらない動き・動作・姿勢に注目すること」
- 「その中に、その人の <心と身体> に関わる特徴や傾向を見いだすこと」
- 「聴覚に消費されるエネルギーを、自らの心身を感じとることに振り向けること」
要点1:「ダンスの力」と「音楽の力」
ダンスは古来より人々の喜怒哀楽と共にあり、また神事の一つとして連綿と伝わってきています。そして、広い意味でのダンスの力を用いて、それを身体心理的な「セラピー」の形式へと展開してきたのが「ダンスセラピー」です。また、ダンスは音楽演奏や楽曲とともにあり、ダンスは音楽のリズムやメロディーと共に互いに高め合い、深め合って発展してきました。
ところが、筆者は次のような展開へと向かうことになりました―。
要点2:制約・義務としての「ダンス」「音楽」から距離をとる
1999年から精神科デイケアで担当し始めた「ダンスセラピー」ですが、スタッフに音楽療法士の方がいて「ミュージック・セラピー」のプログラムがありました。そのため、ダンスセラピーが音楽療法とは異なることが参加者にもはっきりと分かるようにする必要性があり、その結果、次のように進めることにしたのです。
- 音楽はあまり使わず、リズムやカウントが必須ではない「ムーブメント」を中心にダンスセラピーを構成する。
「これは <踊らなくとも良いダンスセラピー> なので、無理に踊らなくても大丈夫ですよ」。「音楽もあまり使わないので、いつもリズムに合わせなくても大丈夫ですよ」。さらに、「私自身、あまり体力が無くてすぐに疲れるので、1-2分もしたら休んだりしますよー」。
そうこうするうちに、あら不思議! 「いつも音楽に合わせて踊ったりする…わけではない」ことにメンバーさんが安心して来てくれるようになりました。また、音源を持ってきて頑張って踊っている元気なメンバーに感嘆したり誉めたりしつつも、「私たちはあまり体力ないからねっ」と「体力なしグループ」の「心の通い合う」仲間ができたりもします。
「…次はじゃー、ダンスほどではないけれど、何となくこんな動き・ムーブメントを、カウントとかしないでやってみましょうかあ!」すると、お付き合いしてくれるメンバーさんが増え、あんまり頑張ったりしなくともいろいろ発見があって楽しんでくれます。結果としては「Dance Movement Therapyプログラム」として大きな効果があり、音楽療法との分離も大成功!となっていきましたー。
*毎回、担当のスタッフさんには「ダンスセラピーって、音楽療法とは違うし、運動療法にも収まっていないですー」「なぜならば…」とミラーニューロンの説明やら、マスローの5段階動機理論とか、ヤーロムの集団療法の「心理療法的」効果11種とかを解説すると、「…なるほど」と分かってくれて26年余…。
*解説として 「ダンスムーブメント・セラピーの心理療法的効果」(PDF) をぜひご一読下さい。
要点3:ダンスセラピー実践技法としてー
ダンスや踊りに含まれないような様々なムーブメントを「自身の <からだとこころ> をより知るために、ボディラーニングとして導入してきました。
「ダンスセラピー・プログラムの前のウォーミングアップ」あるいは「ダンス未然の様々なムーブメントへのトライアル」として「ボディラーニング」レッスンのいくつかをボディラーニング」の場で体験してもらう予定です。楽しめて使いやすいレッスンを中心に紹介する予定です。 例えば―
- 腕の脱力のレッスン
パートナーの方に持ち上げられた私の腕は、スムーズに持ち上げられて、スムーズに落下するでしょうか?! 笑うほど(笑われるほど?!)、力が抜けないー?!
- ※野口体操(『おもさにきく』『からだに聴く』)に触発されたレッスンなど。
(以下、中略)
- 床に横になっての「腕の立ち上げレッスン」
横になった楽な姿勢で腕を立ち上げるとき、腕の重さと動きがよく感じられる―。「腕って重いんだなあ…」。
そして「指・手・手首・肘・肩―」それぞれの動きから、上肢の踊りへと進む…。


- その他…(近々、追加予定)
|